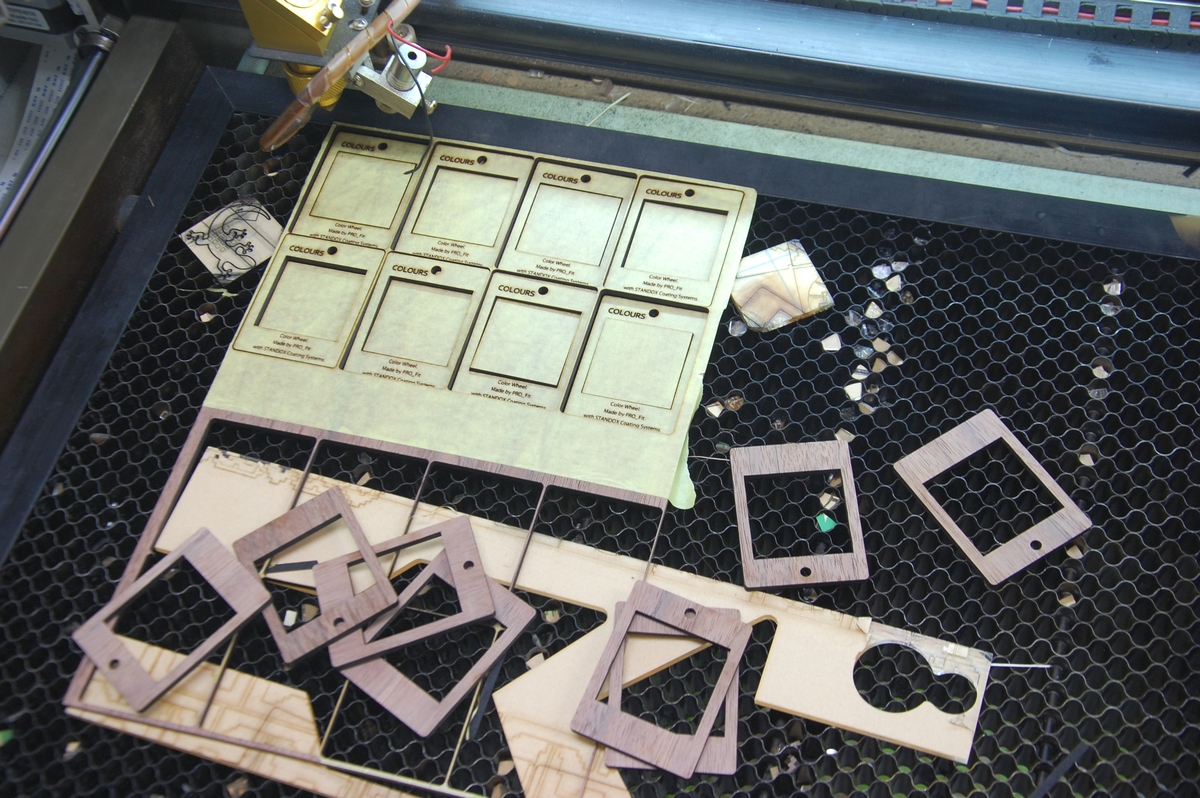自宅のベランダはこれまで余り使う事が無かったので気にしなかったのですが、つくね(保護猫)を迎えてから頻繁にここを利用する事になって、床全体に細かいクラックが生じている事に気が付きました。
自宅のベランダはこれまで余り使う事が無かったので気にしなかったのですが、つくね(保護猫)を迎えてから頻繁にここを利用する事になって、床全体に細かいクラックが生じている事に気が付きました。
 ちゃんと撮影していなかったので判り難いのですが、床に細かいクラックが入っているのが判るかと思います(つくねの毛では無くひび割れています)。
ちゃんと撮影していなかったので判り難いのですが、床に細かいクラックが入っているのが判るかと思います(つくねの毛では無くひび割れています)。
調べてみるとベランダは防水FRPなる物で、使われている塗料はポリエステル樹脂、これが剥き出しになっています。自動車部品で言うと社外品FRP製バンパーのゲルコートままの状態ですから、耐候性の低いこの樹脂がそのまま露出していれば割れてしまうのは当然ですよね。これなら割れる前に耐候性の高い自動車補修用塗料を使って塗っておけば良かったです。
 と言う訳でいつもお世話になっている塗料屋さんに相談してみたところ、こちらがお勧めという事で取り寄せて貰う事に!水性一液性の塗料です。
と言う訳でいつもお世話になっている塗料屋さんに相談してみたところ、こちらがお勧めという事で取り寄せて貰う事に!水性一液性の塗料です。
フローンFRP防水面用アクアトップ – (防水材|トップコート)
 下地処理はいつもと同様ペーパーとスコッチで足付け処理を行い、よく脱脂清掃を行いました。ちなみに塗料の説明書には「アセトンで脱脂」と説明されていて、これはいつも使っているシリコンオフ=ノルマルヘキサンよりかなり強い物ですが(揮発も非常に速い)、なんでだろう?と考えてみたところ、もしかしたらポリエステル樹脂表面を若干溶かしつつ(侵しつつ)、これから塗る塗料の密着性を高めているのかも、と思った次第です。プラモデルの樹脂(PS=ポリスチレン)に塗装を行う際、塗料事態が母材(樹脂部品)を溶かして密着するので足付け処理が必要無いのと同じような感じですかね。
下地処理はいつもと同様ペーパーとスコッチで足付け処理を行い、よく脱脂清掃を行いました。ちなみに塗料の説明書には「アセトンで脱脂」と説明されていて、これはいつも使っているシリコンオフ=ノルマルヘキサンよりかなり強い物ですが(揮発も非常に速い)、なんでだろう?と考えてみたところ、もしかしたらポリエステル樹脂表面を若干溶かしつつ(侵しつつ)、これから塗る塗料の密着性を高めているのかも、と思った次第です。プラモデルの樹脂(PS=ポリスチレン)に塗装を行う際、塗料事態が母材(樹脂部品)を溶かして密着するので足付け処理が必要無いのと同じような感じですかね。
 という感じですが比較的早く終わりました。マスキングから足付け処理、片付けまで含めても3時間といった所です。際や角など塗り難い所は刷毛で、その他はローラーを使いました。いつもやっている塗装とは気にする度合いが1%くらいで済むので、精神的に凄く楽なのは良かったです(笑)。
という感じですが比較的早く終わりました。マスキングから足付け処理、片付けまで含めても3時間といった所です。際や角など塗り難い所は刷毛で、その他はローラーを使いました。いつもやっている塗装とは気にする度合いが1%くらいで済むので、精神的に凄く楽なのは良かったです(笑)。
ちなみにこれを行ったのはまだ涼しい時期で、真夏だったら体力面でもヤバかったと思います(なのでこれからの季節は全くお勧め出来ません!)。
 結果としては良好で、説明書に記載してあったとおり全面に出ていた細かいひび割れは塗装だけで全て埋まりました!パテとかサフェとか要らないなんてまるで夢のような塗料です(笑)。
結果としては良好で、説明書に記載してあったとおり全面に出ていた細かいひび割れは塗装だけで全て埋まりました!パテとかサフェとか要らないなんてまるで夢のような塗料です(笑)。
使ってみた感じとしては、今回の塗料は比較的弾力性があるようで、ひび割れを充填する程に厚塗りしても割れたり感じがしません。現時点で塗り終わってから二カ月程経ち、真夏の熱々の状態に入っても元々あったクラックが出て来る様子は全くありません。塗装後の乾燥(重合)も早く、塗り終わってから半日で使えるというのもGOODです。本当に素晴らしい塗料です!
 尚、ひび割れの原因はやはり紫外線の可能性が高く、こことは別にある3階の余り日が当たらない同じような防水FRPのベランダの床はまだクラックが出ていませんでした。なので今回塗装は行いましたが、出来るだけ真夏の紫外線を遮られるようにとベランダにタープを張る事にしました!
尚、ひび割れの原因はやはり紫外線の可能性が高く、こことは別にある3階の余り日が当たらない同じような防水FRPのベランダの床はまだクラックが出ていませんでした。なので今回塗装は行いましたが、出来るだけ真夏の紫外線を遮られるようにとベランダにタープを張る事にしました!
尚、ベランダには元々ポリカーボネートの庇があるのですが、全体を覆う程のサイズでは無く、なのでつくねが雨の日でもベランダで遊べるよう何かしらを張っておきたかったんですよね。
ただそのままタープシェード等を張るとベランダ面積=天井高が低くなって狭く感じてしまうので、既存の庇にアルミ棒を固定し、柱を延長する事にしました(画像で2本飛び出た棒)。キャンプなどでテントタープを張る際に主柱となるポールを2本立てますが、それと同じ役目のような物です。ただここにポールを立てるのは凄く邪魔だし見た目も良くないので、横から柱を突き出す形としました。
製作時の画像が殆ど無いのですが、使った材料は判るので後日こちらも紹介しようと思います。現時点でタープ張ってから一カ月程経ちますがめっちゃ快適でお勧めです!